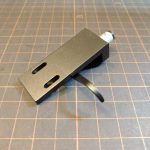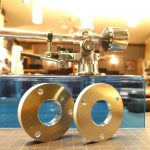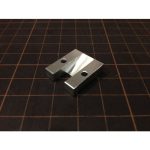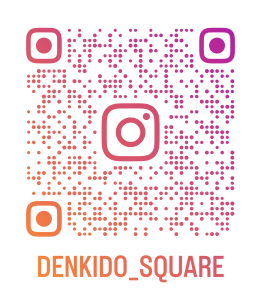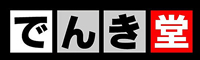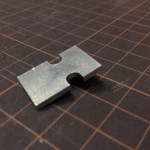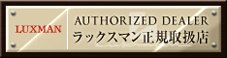いつも当店のご利用誠にありがとうございます、今年も残す所残りわずかとなってまいりました。
当店の年末年始営業時間を下記のとおりとさせていただきます
12/26㈮ ※営業時間変更 11:00~19:00
12/27㈯ 11:00~19:00
12/28㈰ 11:00~19:00
12/29㈪ 13:00~21:00
12/30㈫ 年内最終営業 13:00~21:00
12/31㈬ 定休日
1/1㈭ 元旦 お休み
1/2㈮ お休み
1/3㈯ お休み
1/4㈰ 年始通常営業再開 11:00~19:00
1/5㈪ 通常営業 13:00~21:00
ケーブル加工依頼は12月30日まで、レコードクリーニング作業は12月28日を本年度の締めとさせて頂き、1月4日から受付を再開させて頂きます。予めご了承くださいませ。
お問い合わせはコチラ→0466-20-5223
y