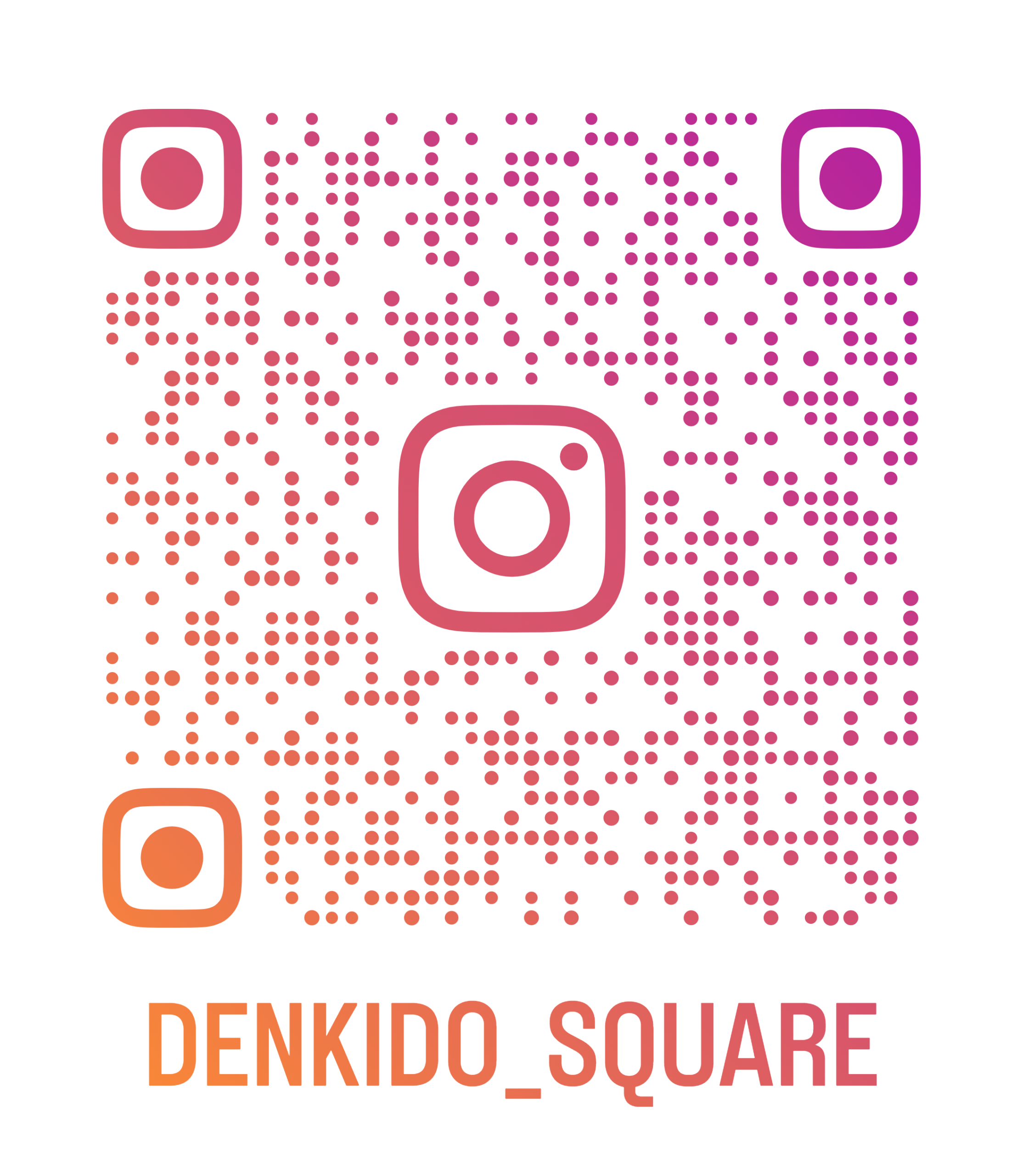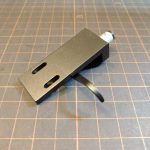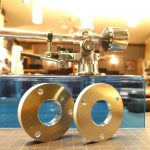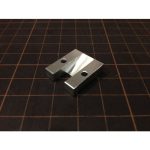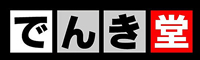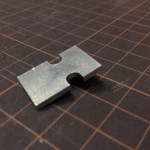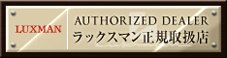これを初めて目にした人たちには、老若男女マニア非マニア問わず、様々な思いを抱かせられずにはいられないであろうこと必須の衝撃的外見を有する、まぁはっきり言えば実にイヤラスィ~外見の電源タップ&ケーブルですね。
ところが困ったことに、この米国生まれの軍事産業の息吹が掛かった極太ケーブルを用いる事で得られる音楽的興奮の度合いが、これまた凄いのなんので、確かに常識的に考えて、こんなのが床じゅうをトグロ巻いたヘビみたくウネってる様な環境なんて、どう考えても一般的には理解され難いでしょうが、一度その音世界を体感してしまうとそうは簡単に諦めたくない世界観だとも思います。
そもそもこちらに限らず、オーディオに関しての電源ケーブルというものは、一度その効果を体感するまではなかなか怪しげな話であり、一度知ってしまえばそれに対して否定的なこと言ってる人間が馬鹿に見えてくる不思議な世界なので、ここでそれをとやかくいう必要は当然無いのですが、定価で199.500円もすれば、そりゃ音質的効果があったぐらいでは「はいそうですか」と容易に購えるものではなくとも、今回程度の良い中古が出て来ましたので、コレはなかなかのチャンスだと私自身も感じましたので、84.000円が予算的に見合う方は聴かずに買っても後悔はされないと思いますよ、ハイ。
しかし太いデスネ、これ。
完売しました。